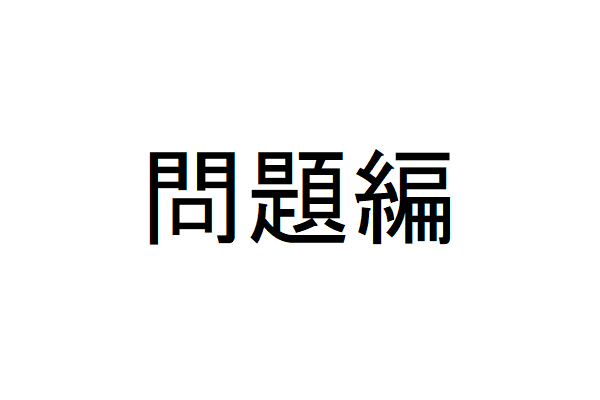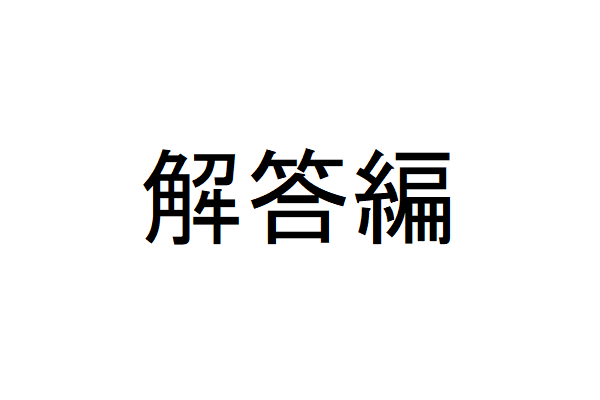このページはモンティホール問題の条件・解答・誤答・類題を記載しています。モンティホール問題は事後確率の問題(情報により確率が更新・再計算される問題。参考:事後確率)です。モンティホール問題は数種の間違い方があることにより異なる間違いを正しいと思い込みやすくなっています。
条件
- 3つのドアのいずれか1つが当たりである。
- 当たりのドアを知らないプレイヤーが最初にドア1つを選択する。
- 次に当たりのドアを知る司会者が他2つの内のはずれのドアを1つ開く。
- 司会者がはずれのドアを1つ開いた後にプレイヤーがドア変更の選択ができる。この時点のそれぞれのドアが当たりの確率。
- (最初の時点で3つのドアが当たりの確率はそれぞれ1/3。)
- (最初にプレイヤーが選択したドアが当たりのときに司会者が他2つのドアを開く確率はそれぞれ1/2。)
- 3つのドアをドアA,B,Cとし、プレイヤーが最初にドアAを選択するものとする。
| 事象 | ありえる度合 | 確率 |
|---|
| ドアAが当たり | ドアAが当たりかつ司会者がドアBを開く | 1/3x1/2 = 1/6 | 1/3 | 1/3 |
| ドアAが当たりかつ司会者がドアCを開く | 1/3x1/2 = 1/6 |
| ドアBが当たり | ドアBが当たりかつ司会者がドアCを開く | 1/3x1 = 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| ドアCが当たり | ドアCが当たりかつ司会者がドアBを開く | 1/3x1 = 1/3 | 1/3 | 1/3 |
- プレイヤーがドアAを選択した後に司会者がドアCを開いた場合とする。
解答
司会者がドアCを開いたことによりドアCが当たりの場合とドアAが当たりかつ司会者がドアBを開く場合が排除されて、ドアAが当たりかつ司会者がドアCを開く場合のありえる度合(1/3x1/2=1/6)とドアBが当たりかつ司会者がドアCを開く場合のありえる度合(1/3x1=1/3)の比率により、ドアA,Bが当たりの確率が1/3,2/3となる。
| 事象 | ありえる度合 | 確率 |
|---|
| ドアAが当たり | ドアAが当たりかつ司会者がドアBを開く | 1/3x1/2 = 1/6 | 1/6 | 1/3 |
| ドアAが当たりかつ司会者がドアCを開く | 1/3x1/2 = 1/6 |
| ドアBが当たり | ドアBが当たりかつ司会者がドアCを開く | 1/3x1 = 1/3 | 1/3 | 2/3 |
| ドアCが当たり | ドアCが当たりかつ司会者がドアBを開く | 1/3x1 = 1/3 | | |
直感的な理解
プレイヤーが最初に選んだドアAが当たりで司会者がたまたまドアCを開いた場合よりドアBが当たりで確定してドアCを開いた場合の方がありえる。よって、司会者がドアCを開いたときドアAが当たりの確率よりドアBが当たりの確率の方が高い。
図解
※画像クリックで再描画
問題編
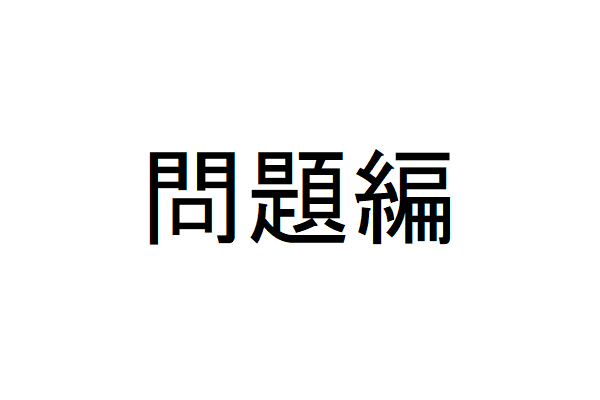
解答編
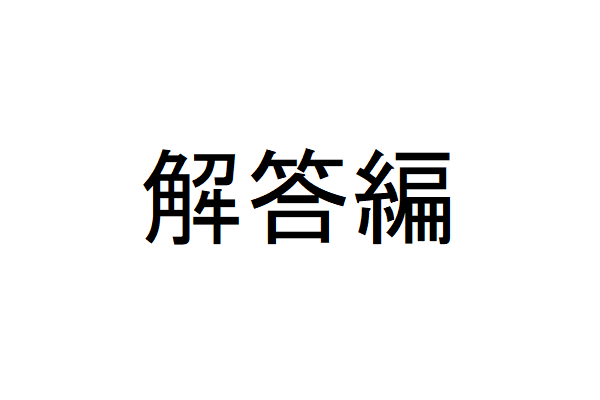
誤答
- プレイヤーが最初に選んだドアAが当たりの確率は変化しないため残ったドアに変更すれば当たりの確率は2/3となる。
- ドアのグループにおいて一つを残して他を開けることで確率が集束されるため残ったドアBが当たりの確率が2/3となる。
- プレイヤーが最初に選んだドアがはずれである確率は2/3のため残ったドアに変更した場合の当たりの確率は2/3である。
- 最初に選んでないドアB,Cいずれかが当たりならば残ったドアは当たりだから選択を変更すれば2/3の確率で当たりである。
- ドアを変更しないかするかという選択は最初の時点のドアAとドアB,Cのどちらにするかという選択と同じである。
- 最初にプレイヤーが当たりのドアを選択する確率は1/3ではずれを選択する確率は2/3だから変更すれば当たりの確率は2/3。
- 司会者がドアを開く前の時点でドアAが当たりの確率は1/3。ドアAが当たりかつ司会者がドアBを開く確率は1/3x1/2、ドアAが当たりかつ司会者がドアCを開く確率は1/3x1/2。司会者がドアを開いた時のドアAが当たりの確率は二通りの場合の確率を足した1/3x1/2+1/3x1/2=1/3。
- ドアAが当たりかつ司会者がはずれのドアを開く度合(1/3x1=1/3)とドアB,Cのいずれかが当たりかつ司会者がはずれのドアを開く度合(2/3x1=2/3)の比率により、ドアAが当たりの確率が1/3となる。
- 司会者がドアCを開いたことで当たりのドアはA,Bのいずれかとなるため、ドアA,Bの当たりの確率が1/2ずつとなる。
- ドアBが当たりの場合も司会者はドアB,Cのいずれかを開くから、ドアAが当たりかつ司会者がドアCを開く度合(1/3x1/2=1/6)とドアBが当たりかつ司会者がドアCを開く度合(1/3x1/2=1/6)の比率により、ドアA,Bの当たりの確率が1/2ずつとなる。
- ドアAが当たりの場合も司会者は確定してドアCを開くから、ドアAが当たりかつ司会者がドアCを開く度合(1/3x1=1/3)とドアBが当たりかつ司会者がドアCを開く度合(1/3x1=1/3)の比率により、ドアA,Bの当たりの確率が1/2ずつとなる。
モンティホール問題は数種の間違い方があり、残った2つのドアの違いがないものとする間違い、司会者がドアを開くこと(司会者が開いたドアの情報)でプレイヤーが選んだドアが当たりの確率が変化しないという間違い、プレイヤーが選んだ時点で当たりはずれが確定するという間違い、司会者がドアを開いたという状況・条件を認識できていない間違いがあります。
特に、司会者がドアを開いたという状況・条件を認識できていない間違いは、問題の条件そのものを間違えており異なる確率を設定された場合においても違えた条件においては回答が合ってしまうこともあり間違いに気付くことは難しくなっています。また、本誤答が正しいとされることが多いことにより、状況・条件を間違っている回答が正答扱いされているとは思わず、司会者がドアを開くことでプレイヤーが選んだドアが当たりの確率が変化しないという誤答が発生しやすくなっている可能性があります。
類題1
条件
- 11個の球のいずれか1つが当たりである。
- 3つの箱の中に6,4,1個ずつ球を入れる。
- 当たりの球が入った箱1つが当たりである。
- 当たりの箱を知らないプレイヤーが最初に箱1つを選択する。
- 次に当たりの箱を知る司会者が他2つの内のはずれの箱を1つ開く。
- 司会者がはずれの箱を1つ開いた後にプレイヤーが箱変更の選択ができる。この時点のそれぞれの箱が当たりの確率。
- (最初の時点で3つの箱が当たりの確率はそれぞれ6/11,4/11,1/11。)
- (最初にプレイヤーが選択した箱が当たりのときに司会者が他2つの箱を開ける確率はそれぞれ1/2。)
- 当たりの確率6/11,4/11,1/11の3つの箱を箱A,B,Cとし、プレイヤーが最初に箱Aを選択するものとする。
| 事象 | ありえる度合 | 確率 |
|---|
| 箱Aが当たり | 箱Aが当たりかつ司会者が箱Bを開く | 6/11x1/2 = 3/11 | 6/11 | 6/11 |
| 箱Aが当たりかつ司会者が箱Cを開く | 6/11x1/2 = 3/11 |
| 箱Bが当たり | 箱Bが当たりかつ司会者が箱Cを開く | 4/11x1 = 4/11 | 4/11 | 4/11 |
| 箱Cが当たり | 箱Cが当たりかつ司会者が箱Bを開く | 1/11x1 = 1/11 | 1/11 | 1/11 |
- プレイヤーが箱Aを選択した後に司会者が箱Cを開いた場合とする。
解答
司会者が箱Cを開いたことにより箱Cが当たりの場合と箱Aが当たりかつ司会者が箱Bを開く場合が排除されて、箱Aが当たりかつ司会者が箱Cを開く場合のありえる度合(6/11x1/2=3/11)と箱Bが当たりかつ司会者が箱Cを開く場合のありえる度合(4/11x1=4/11)の比率により、箱A,Bが当たりの確率が3/7,4/7となる。
| 事象 | ありえる度合 | 確率 |
|---|
| 箱Aが当たり | 箱Aが当たりかつ司会者が箱Bを開く | 6/11x1/2 = 3/11 | 3/11 | 3/7 |
| 箱Aが当たりかつ司会者が箱Cを開く | 6/11x1/2 = 3/11 |
| 箱Bが当たり | 箱Bが当たりかつ司会者が箱Cを開く | 4/11x1 = 4/11 | 4/11 | 4/7 |
| 箱Cが当たり | 箱Cが当たりかつ司会者が箱Bを開く | 1/11x1 = 1/11 | | |
最初の時点での箱Aが当たりの確率6/11(>1/2)より、司会者が箱を開くという状況での場合(司会者がどちらの箱を開けるかによらず再選択を決定する場合)ではプレイヤーは箱Aのままの方が当たりの確率が高いが、司会者が箱Cを開いた状況での場合では箱Aから箱Bに選択を変えた方が当たりの確率が高い。司会者がどちらの箱を選び開けたかという情報が確率に作用していることがわかる。再選択の時点では司会者がどちらの箱を選び開けたかという情報を得ているため、その情報を得た状態での確率を考えねばならない。
類題2
条件
- 司会者がトランプのカード3枚、ダイヤのA,2,3を伏せて並べる。
- 並びを知らないプレイヤーが最初にカード1枚を選択する。
- 次に並びを知る司会者が他2枚の内からダイヤのAを避けて1枚選んでめくる。
- プレイヤーが最初に選んだカードがダイヤのAであるときに司会者はダイヤの2,3をそれぞれ2/7,5/7の確率で選びめくることが知られている。
- 司会者が1枚めくった後にプレイヤーがカードを再選択できる。この時点のそれぞれのカードがダイヤのAである確率。
| 事象 | ありえる度合 | 確率 |
|---|
| プレイヤーが最初に選択したカードがダイヤのA | 司会者がダイヤの2をめくる | 1/3x2/7 = 2/21 | 1/3 | 1/3 |
| 司会者がダイヤの3をめくる | 1/3x5/7 = 5/21 |
| プレイヤーが最初に選択したカードがダイヤの2 | 司会者がダイヤの3をめくる | 1/3x1 = 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| プレイヤーが最初に選択したカードがダイヤの3 | 司会者がダイヤの2をめくる | 1/3x1 = 1/3 | 1/3 | 1/3 |
- プレイヤーがカード1枚を選択した後に司会者がダイヤの3をめくった場合とする。
解答
司会者がダイヤの3をめくったことによりプレイヤーが最初に選択したカードがダイヤの3である場合とプレイヤーが最初に選択したカードがダイヤのAかつ司会者がダイヤの2をめくる場合が排除されて、プレイヤーが最初に選択したカードがダイヤのAかつ司会者がダイヤの3をめくる場合のありえる度合(1/3x5/7=5/21)とプレイヤーが最初に選択したカードがダイヤの2かつ司会者がダイヤの3をめくる場合のありえる度合(1/3x1=1/3)の比率により、プレイヤーが最初に選択したカードがダイヤのAである確率と残ったカードがダイヤのAである確率が5/12,7/12となる。
| 事象 | ありえる度合 | 確率 |
|---|
| プレイヤーが最初に選択したカードがダイヤのA | 司会者がダイヤの2をめくる | 1/3x2/7 = 2/21 | 5/21 | 5/12 |
| 司会者がダイヤの3をめくる | 1/3x5/7 = 5/21 |
| プレイヤーが最初に選択したカードがダイヤの2 | 司会者がダイヤの3をめくる | 1/3x1 = 1/3 | 1/3 | 7/12 |
| プレイヤーが最初に選択したカードがダイヤの3 | 司会者がダイヤの2をめくる | 1/3x1 = 1/3 | | |
司会者がダイヤの3のカードをめくった時点で、残った2枚のカードはダイヤのAまたはダイヤの2のどちらかとなる。めくられたダイヤの3のカードではないという情報のみを考えたら残った2枚のカードがダイヤのAである確率は1/2ずつとなる。もう一つの情報、司会者がダイヤの3のカードを選びめくったことを考えると、プレイヤーが最初に選択したカードがダイヤのAである場合は5/7の確率でダイヤの3を選びめくった、他1枚のカードがダイヤのAである場合は確定してダイヤの3を選びめくった、この比率から司会者がダイヤの3をめくったときにプレイヤーが最初に選択したカードがダイヤのAである確率は5/12、他1枚のカードがダイヤのAである確率は7/12と求まる。
プレイヤーが最初に選ばなかったカード2枚の内の1枚がめくられたことでプレイヤーが最初に選んだカードがダイヤのAである確率が変化すること、司会者の選び方が確率に作用していることがわかる。(司会者の選び方によってはプレイヤーが最初に選んだカードがダイヤのAである確率が1/2や1/3になることがある。)
類題3
条件
- 白玉赤玉が2:5の割合で入った袋A、赤玉のみが入った袋B、白玉のみが入った袋Cがある。
- プレイヤーが袋を1つ選択する。
- 次にプレイヤーが袋から玉を1つ取り出す。この時点のプレイヤーが選んだ袋が袋Aである確率。
| 事象 | ありえる度合 | 確率 |
|---|
| プレイヤーが選択した袋が袋A | 白玉を取り出す | 1/3x2/7 = 2/21 | 1/3 | 1/3 |
| 赤玉を取り出す | 1/3x5/7 = 5/21 |
| プレイヤーが選択した袋が袋B | 赤玉を取り出す | 1/3x1 = 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| プレイヤーが選択した袋が袋C | 白玉を取り出す | 1/3x1 = 1/3 | 1/3 | 1/3 |
- プレイヤーが取り出した玉が赤玉である場合とする。
解答
赤玉を取り出したことによりプレイヤーが選択した袋が白玉のみが入った袋Cである場合とプレイヤーが選択した袋が袋Aかつ白玉を取り出す場合が排除されて、プレイヤーが選択した袋が袋Aかつ赤玉を取り出す度合(1/3x5/7=5/21)、プレイヤーが選択した袋が袋Bかつ赤玉を取り出す度合(1/3x1=1/3)の比率により、プレイヤーが選択した袋が袋Aである確率が5/12となる。
| 事象 | ありえる度合 | 確率 |
|---|
| プレイヤーが選択した袋が袋A | 白玉を取り出す | 1/3x2/7 = 2/21 | 5/21 | 5/12 |
| 赤玉を取り出す | 1/3x5/7 = 5/21 |
| プレイヤーが選択した袋が袋B | 赤玉を取り出す | 1/3x1 = 1/3 | 1/3 | 7/12 |
| プレイヤーが選択した袋が袋C | 白玉を取り出す | 1/3x1 = 1/3 | | |
プレイヤーが玉を取り出す前、玉の情報を得る前の時点ではそれぞれの袋を選んでいる確率が1/3ずつだったのが、取り出した玉が赤玉である情報を得ることにより確率が変化するということがわかる。また、赤玉白玉の入っている割合が袋Aを選んでいる確率に作用することがわかる。
類題4
条件
- 赤,青,黄の3個のスイッチがあり、1個と2個のグループに分かれており、スイッチを1個入れると他方のグループのいずれかのスイッチと同色のランプが点灯する。
- グループ分けを知らないプレイヤーが1個スイッチを入れて、ランプが点灯した時点のそれぞれのスイッチが1個のグループである確率。
- (最初の時点で3個のスイッチが1個のグループである確率はそれぞれ1/3。)
- (1個のグループのスイッチを入れたときに2個のグループのうちで点灯するランプの色の確率はそれぞれ1/2。)
- プレイヤーが赤スイッチを入れるものとする。
| 事象 | ありえる度合 | 確率 |
|---|
| 赤スイッチが1個のグループ | 青ランプが点灯する | 1/3x1/2 = 1/6 | 1/3 | 1/3 |
| 黄ランプが点灯する | 1/3x1/2 = 1/6 |
| 青スイッチが1個のグループ | 青ランプが点灯する | 1/3x1 = 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 黄スイッチが1個のグループ | 黄ランプが点灯する | 1/3x1 = 1/3 | 1/3 | 1/3 |
- 赤スイッチを入れて青ランプが点灯した場合とする。
解答
青ランプが点灯したことにより黄スイッチが1個のグループである場合と赤スイッチが1個のグループかつ黄ランプが点灯する場合が排除されて、赤スイッチが1個のグループかつ青ランプが点灯する場合のありえる度合(1/3x1/2=1/6)と青スイッチが1個のグループかつ青ランプが点灯する場合のありえる度合(1/3x1=1/3)の比率により、赤,青スイッチが1個のグループである確率が1/3,2/3となる。
| 事象 | ありえる度合 | 確率 |
|---|
| 赤スイッチが1個のグループ | 青ランプが点灯する | 1/3x1/2 = 1/6 | 1/6 | 1/3 |
| 黄ランプが点灯する | 1/3x1/2 = 1/6 |
| 青スイッチが1個のグループ | 青ランプが点灯する | 1/3x1 = 1/3 | 1/3 | 2/3 |
| 黄スイッチが1個のグループ | 黄ランプが点灯する | 1/3x1 = 1/3 | | |